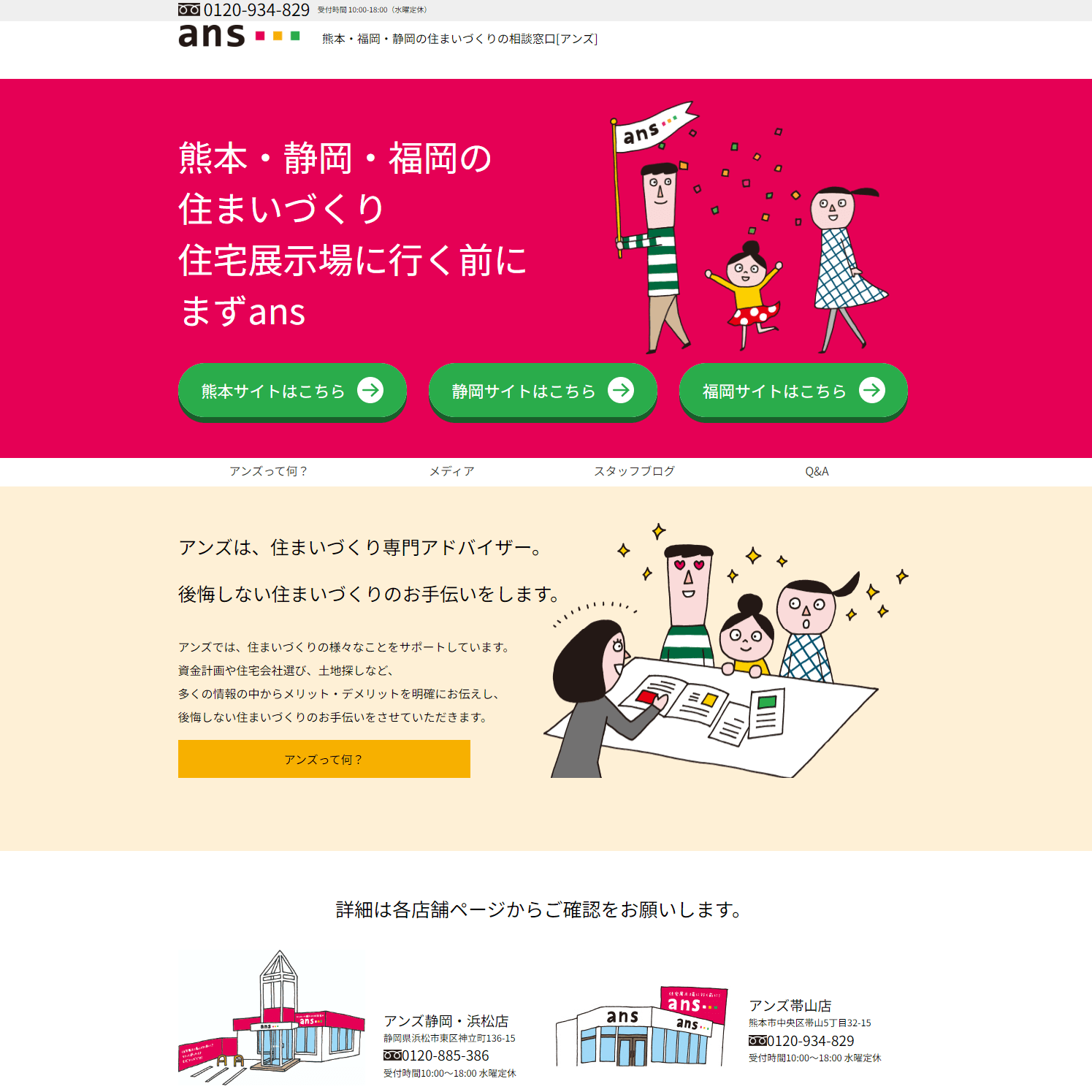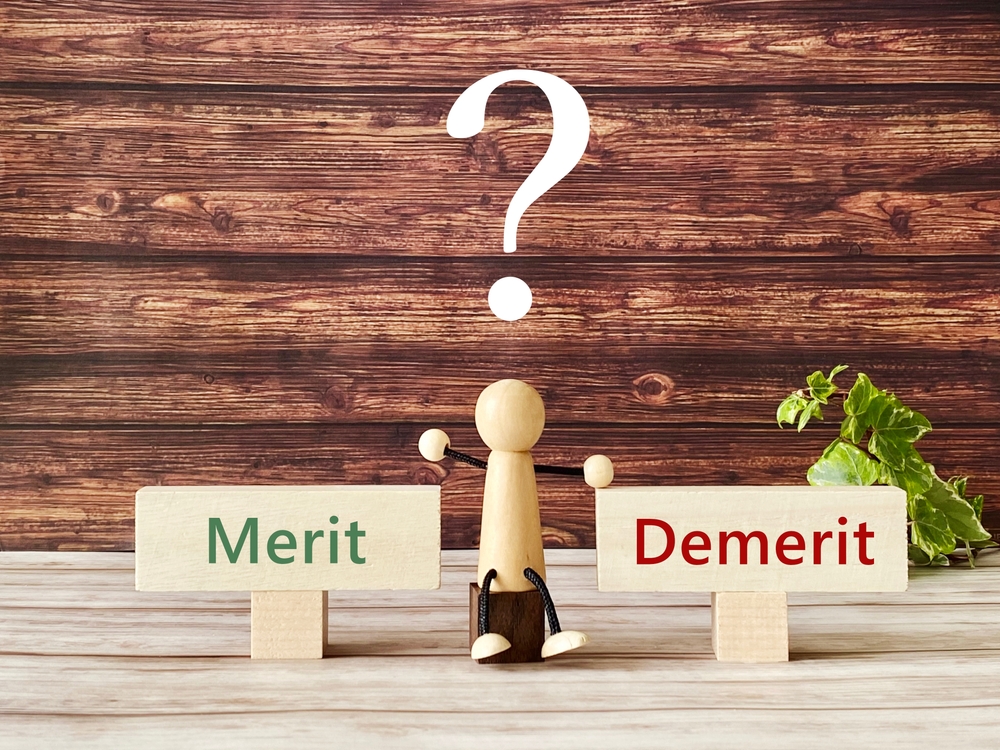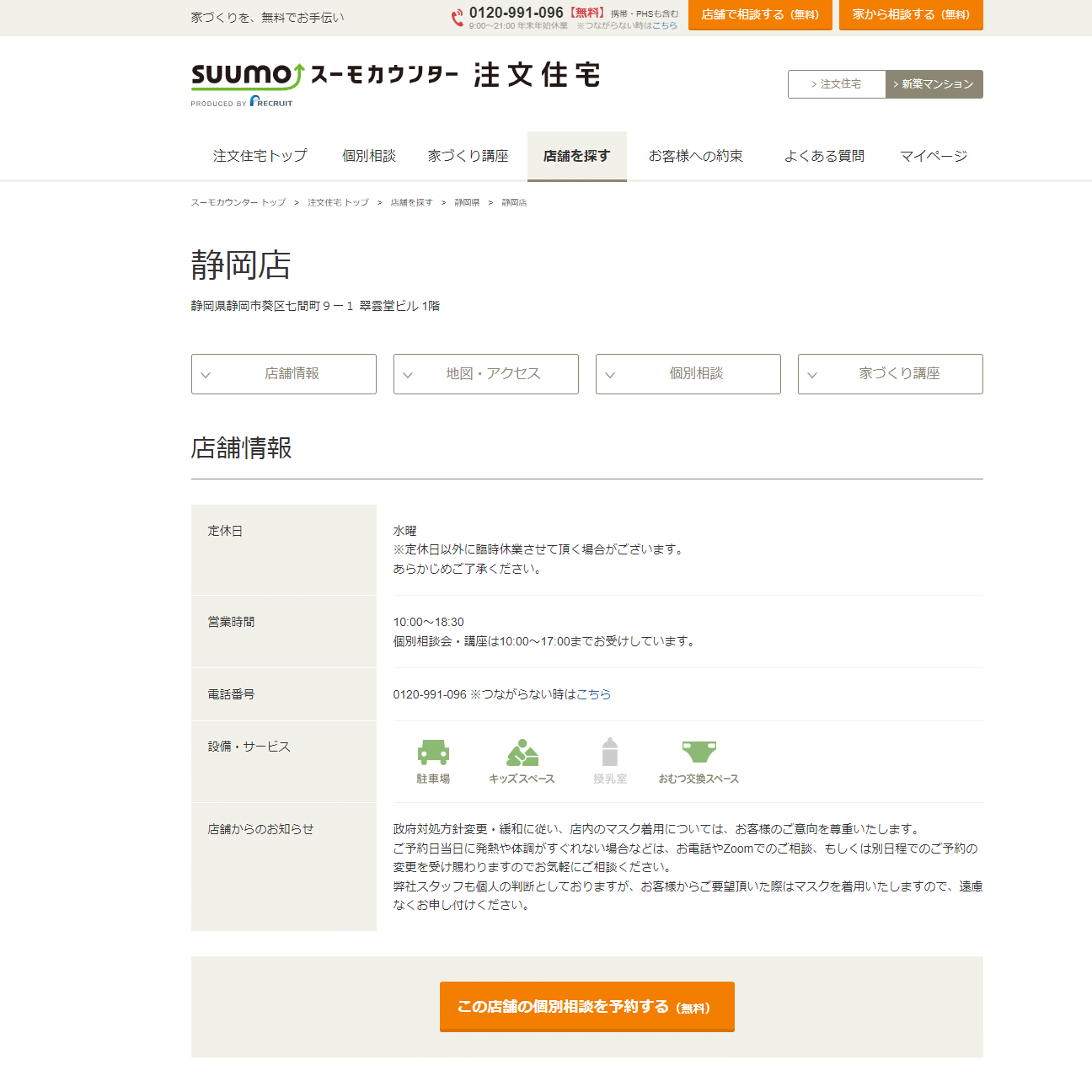二世帯住宅には子育ての負担軽減や生活のサポートなど、さまざまなメリットがあります。一方で生活習慣の違いによるストレスや費用負担のトラブルなど、デメリットも少なくありません。
親との同居を考える際は、将来を踏まえるのはもちろん、費用負担についてルールを決めておくことが重要です。
本記事では、二世帯住宅のメリット・デメリットを詳しく解説するとともに、後悔しないための解決策について紹介します。
二世帯住宅のメリット
二世帯住宅には家族のコミュニケーションを増やしつつ、建築・生活コストの負担を減らせるメリットがあります。また、同居することで光熱費などの生活費を節約できるほか、住宅取得にかかる費用も抑えることが可能です。
さらには税制面での優遇措置も受けられるため、経済的なメリットは大きいといえるでしょう。ここでは、二世帯住宅の主なメリットを3つ解説します。
親が孫の子育てを手伝ってくれる
共働き世帯にとって子育ての負担は大きな悩みのひとつです。仕事と育児の両立は容易ではなく、とくに小さな子供がいる場合は送り迎えや食事の準備など、日々の家事に追われてしまいます。
しかし、二世帯住宅であれば親世帯に子育ての手助けをしてもらうことが可能です。祖父母が孫の面倒を見てくれることで、共働き夫婦の負担は大幅に軽減されます。
また、子供にとっても祖父母との触れ合いを通じて、情緒面での成長が期待できるでしょう。
それぞれの生活をカバーし合える
二世帯住宅では、親子世帯がお互いの生活をサポートし合えるのも大きなメリットです。たとえば、旅行や出張で家を留守にする際は、一方の世帯が家の管理をしてくれるので安心できます。
郵便物の受け取りや宅配便の対応なども任せられるほか、家事や庭の手入れなど得意分野を分担することで、両世帯の負担を減らすことができるでしょう。
また、親世帯の高齢化に伴い、将来的には介護の必要性も出てくるかもしれません。その際も子世帯が近くにいれば、すぐに対応してもらえるので心強いはずです。
税金と補助金の経済的な負担が軽くなる
二世帯住宅を建てると、税制面での優遇措置を受けることが可能です。たとえば、住宅ローン控除の適用を受ければ、一定期間は所得税や住民税が減額されます。
また、親世帯の住宅取得資金を子世帯に贈与した場合、一定の要件を満たせば贈与税が非課税になるほか、二世帯住宅の建築やリフォームに関しては補助金制度も用意されています。
制度の内容は自治体によって異なりますが、数十万円から数百万円の補助を受けることも可能です。
二世帯住宅のデメリット
二世帯住宅にはメリットがある一方で、デメリットも存在します。なかでも大きな課題となるのは、生活習慣の違いに起因するストレスです。
親世帯と子世帯では生活リズムや価値観が異なるため、お互いの考え方のズレから軋轢が生じやすくなります。また、住宅ローンや光熱費など、費用負担のトラブルも起こりがちです。
さらには将来的に家を売却する際にも、二世帯住宅ならではの困難が伴います。二世帯住宅を検討する際はメリットだけでなく、デメリットについても十分に理解しておく必要があるでしょう。
ここでは、二世帯住宅の主なデメリットを3つ解説します。
生活習慣の違いがストレスになる可能性がある
二世帯住宅のデメリットとしては、生活習慣の違いからくるストレスが挙げられます。親世帯と子世帯では生活リズムや食事の好み、子育ての方針など、さまざまなシーンで価値観の相違があるのが普通です。
とくに夫の親と同居する場合、妻にとっては義父母との関係構築が大きな負担となります。些細なことの積み重ねでも、長期的には深刻なストレスに発展しかねません。
こうしたストレスを軽減するには、同居前に両世帯で十分な話し合いをおこない、生活のルールを決めておくことが重要です。
費用負担で揉めやすい
二世帯住宅では住宅ローンや光熱費、食費など、さまざまな費用の負担割合を決めなければなりません。この際、親世帯と子世帯の収入格差から、費用負担のトラブルが生じることがあります。
たとえば、住宅ローンを親子で分担する場合、途中で親の収入が減ったり子供が失業したりすると、残りの負担が一方に偏ってしまいます。また、光熱費などの変動費については、使用量に応じて公平に分担することが難しい面もあるでしょう。
こうしたトラブルを避けるには定期的に話し合いの場を設け、必要に応じてルールを決めておくことが大切です。
ローン返済や売却するときにトラブルに発展しやすい
二世帯住宅を建てる際は、住宅ローンを組む場合があります。親子で負担を分担すると、一時的には支払いが楽になりますが、将来的なリスクが伴うことを理解しておくべきです。
たとえば、親の死亡や子供の転勤など予期せぬ事態が起これば、ローンの返済が困難になる可能性があります。また、将来的に家を売却する際にも問題が生じがちです。
二世帯住宅は一般的な住宅に比べて買い手が限られるため、思うように売れないことがあります。売却が難航すれば、親子間のトラブルに発展するおそれがあるので注意が必要です。
二世帯住宅を検討する際は、メリットだけでなく将来的なリスクについても考慮しなければなりません。
二世帯住宅に後悔しないための解決策
二世帯住宅に後悔しないための解決策としては、二世帯住宅に特化したメーカーを選ぶこと、将来を踏まえて検討すること、費用を負担する際のルールを決めておくことが挙げられます。
ここでは、3つの解決策について詳しく解説します。
二世帯住宅に特化したメーカーを選ぶ
二世帯住宅を建てる際は、二世帯住宅の設計に強いハウスメーカーを選ぶことが重要です。一口に二世帯住宅といっても、家族構成やライフスタイルによって求められる間取りは違います。
プライバシーを重視するのか、家族との交流を大切にするのか、それぞれの要望に合わせた提案が必要です。
二世帯住宅の実績が豊富なハウスメーカーなら、こうした要望を的確に汲み取り、最適なプランを提示してくれます。また、親世帯と子世帯の意見の食い違いを調整するのも、ハウスメーカーの重要な役割です。
二世帯住宅の建築は、一般住宅よりも専門的な知識とノウハウが求められます。信頼できるハウスメーカーを選び、満足のいく住宅を建てましょう。
将来を踏まえて検討する
二世帯住宅を建てる際は、将来的な変化も見据えて計画を立てることが大切です。
たとえば、親世帯の高齢化に伴い、バリアフリー設計の必要性が高まるかもしれません。介護を見据えて、あらかじめ手すりの設置や段差の解消を施しておくといいでしょう。
また、子供の成長に合わせて、子ども部屋を増やすことも視野に入れておく必要があります。家族構成の変化に柔軟に対応できるよう、間取りに融通性を持たせておくことが重要です。
費用を負担する際のルールを決めておく
二世帯住宅では住宅ローンや光熱費、食費など、さまざまな費用負担が発生します。トラブルを避けるためには、これらの費用を誰がどのように負担するのか、事前にルールを決めておくことが重要です。
とくに住宅ローンについては親子の収入バランスを考慮したうえで、無理のない返済プランを立てる必要があります。万が一、どちらかの収入が途絶えた場合の対応策も話し合っておきましょう。
二世帯住宅の種類
まずは、二世帯住宅の種類について解説します。二世帯住宅は「完全同居型二世帯住宅」「完全分離型二世帯住宅」「一部共有型二世帯住宅」の三種類に分類できます。以下で、それぞれの特徴やメリット、デメリットを紹介するので、ぜひご覧ください。
完全同居型二世帯住宅
完全同居型は、寝室などの個室を除き、リビング、キッチン、浴室、トイレといった生活空間のほぼすべてを親世帯と子世帯で共有するスタイルです。最大のメリットは、建築コストとランニングコストを大幅に抑えられる点です。水回りなどの設備が世帯ごとに不要なため、建築費用が他の二世帯住宅の形態に比べて安価になります。
また、光熱費も一本化されるため管理がしやすく、経済的な負担を軽減できるでしょう。日常的に顔を合わせることで家族間のコミュニケーションが活発になり、家事や育児、将来的な介護においても自然な形で協力体制を築きやすいのが魅力です。特に共働きの世帯にとっては、子どもの面倒を祖父母に見てもらえる安心感は大きいでしょう。
一方で、最大のデメリットはプライバシーの確保が難しいことです。生活空間が共有されるため、一人の時間や夫婦だけの時間を持ちにくく、生活リズムや価値観の違いが日々のストレスに直結する可能性があります。また、光熱費の支払い方法など、金銭面のトラブルも想定されます。
トラブルを防止するために、家族内で事前にルールを決めておくようにしましょう。お互いの生活スタイルを尊重し、密なコミュニケーションを苦としない家族に向いているタイプです。
完全分離型二世帯住宅
完全分離型は、玄関からLDK、水回りまで、すべての生活機能を世帯ごとに完全に分けたスタイルです。一つの建物の中に二つの独立した住戸が隣接、あるいは上下に重なっているイメージで、内部で行き来できる間取りもあれば、外階段などで動線を完全に分ける設計もあります。
このタイプの最大のメリットは、各世帯のプライバシーと独立性が確保されることです。生活リズムや価値観の違いを気にする必要がほとんどなく、光熱費のメーターを分ければ費用負担が明確になり、金銭的なトラブルも避けやすいでしょう。
その反面、デメリットとしては建築コストが最も高額になる点が挙げられます。すべての設備を2つずつ設置するため、費用がかさみ、広い敷地も必要になります。また、生活が完全に分離しているため、意識的に交流しないとコミュニケーションが希薄になるでしょう。
介護や子育てなどの問題を抱える家族にとって、ストレスを限りなく軽減できる選択肢と言えるでしょう。
一部共有型二世帯住宅
一部共有型は「完全同居型」と「完全分離型」の中間に位置するタイプで、玄関、浴室、キッチン、LDKなど、生活空間の一部のみを両世帯で共有します。どこを共有し、どこを分離させるかは家族のライフスタイルに合わせて自由に設計できるのが特徴です。
例えば、玄関のみを共有してプライバシーを高めたり、浴室とLDKを共有してコミュニケーションの機会を増やしたりと、柔軟なプランニングが可能です。
このタイプのメリットは、コストとプライバシーのバランスを取りやすい点にあります。共有部分を設けることで建築コストを分離型より抑えつつ、各世帯のプライベート空間もしっかり確保できるのが特徴です。共有スペースで顔を合わせることで自然なコミュニケーションが生まれ、必要なときには協力し合える「程よい距離感」を保てるでしょう。
ただし、共有部分の利用時間や掃除の分担、来客時のルールなどを事前に家族でしっかり話し合って決めないと、トラブルの原因になってしまうので注意が必要です。コストを抑えながらもお互いのプライバシーを尊重し、協力し合える関係を築きたいと考える多くの家族にとって現実的な選択肢と言えるでしょう。
二世帯住宅に関する補助金について
ここからは、二世帯住宅を検討している方に向けて、利用できる補助金を紹介します。具体的な補助金制度として「地域型住宅グリーン化事業」「長期優良住宅化リフォーム推進事業」「地域の住宅補助」の3つが挙げられます。これらの補助金を活用することで、お得に住宅づくりを進められるでしょう。
申請を漏らしてしまうと、助成金を受け取れないことも多いので、制度の適用可否を事前に確認してください。では、それぞれについて詳しくみていきましょう。
地域型住宅グリーン化事業
地域型住宅グリーン化事業は、国土交通省が主導する補助金制度です。地域の木材関連事業者や建材流通業者、中小工務店などが連携してグループを組み、省エネルギー性能や耐久性などに優れた木造住宅を建てる際に支援することを目的としています。
個人が直接申請するのではなく、この事業に採択された「グループ」に所属する工務店を通じて補助金が交付されるのが特徴です。対象となるのは、長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)といった国が定める高い性能基準を満たす住宅です。二世帯住宅も、これらの基準を満たせば補助の対象となるので確認しましょう。
特にこの事業には、親世帯、子世帯、孫世帯が同居する「三世代同居対応」や、地域の木材を活用した場合の加算措置が設けられており、二世帯住宅との親和性が高いのが特徴です。
補助金を活用することで、高性能な住宅を建てる際に初期費用を抑えながら、快適な住環境を実現できます。ただし、どの工務店でも利用できるわけではないため、家づくりを依頼する工務店がこの事業の採択グループに属しているかを確認する必要があります。
長期優良住宅化リフォーム推進事業
長期優良住宅化リフォーム推進事業は、既存の住宅を長く、快適に、安心して使い続けるために、質の高いリフォーム工事を支援する国の補助金制度です。主に、住宅の性能を向上させる工事が対象となります。例えば、親世帯が住んでいる家を子世帯と同居するために二世帯住宅へリフォームする場合などに活用できます。
この事業を利用するには、まず専門家による住宅診断を受け、住宅の現状把握が必要です。そのうえで「耐震性の向上」「省エネルギー対策(断熱改修など)」「劣化対策(雨漏り防止など)」「バリアフリー化」といった性能向上リフォームを実施することで、工事費用の一部が補助されます。
二世帯住宅との関連で注目すべきは、補助額が加算される「三世代同居対応改修工事」のメニューがある点です。キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかを増設する工事が対象となり、二世帯住宅化リフォームの費用負担を軽減できます。古い住宅の性能を向上させ、安心で快適な二世帯住宅を実現したい場合に非常に有効な制度と言えるでしょう。
地域の住宅補助
国の制度とは別に、各都道府県や市区町村が独自に設けている住宅関連の補助金・助成金制度も数多く存在します。「三世代同居・近居支援」「子育て世帯定住促進」「地元産材利用促進」といった目的の補助金が、結果的に二世帯住宅の建築やリフォームに適用できる場合が多いので、チェックしてみましょう。
三世代が同居や近隣に住むための住宅を取得・リフォームする費用の一部を助成する制度や、子育て世帯の住宅取得費用を補助する制度など、内容は自治体によってさまざまです。
また、地域の林業を活性化させる目的で、その地域で伐採された木材を一定量以上使って家を建てる場合に補助金が出る制度も、二世帯住宅で活用できる可能性があります。これらの補助金は、国の制度と併用できる場合もあるため、適用可能であれば大きなメリットになるでしょう。
ただし、多くの制度は予算や件数に限りがあったり、申請期間が短かったりするため、家づくりの計画段階から自治体のホームページなどで情報収集を始めるようにしてください。
まとめ
二世帯住宅は親子のコミュニケーションを深められるメリットがある一方で、生活習慣の違いによるストレスや、費用負担のトラブルなど、さまざまなデメリットがあります。
これらの問題は事前に対策を立てることで、ある程度は回避できます。家族で十分に話し合い、ルールを決めておきましょう。
二世帯住宅の設計については住宅相談窓口に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。不安を抱えたまま家を建てるのではなく、専門家の知見を借りながら後悔のない二世帯住宅を実現しましょう。
-
 引用元:https://shizuoka-ouchisodan.com
家づくりに関することを1から相談できる!
引用元:https://shizuoka-ouchisodan.com
家づくりに関することを1から相談できる!-
Point
完全無料で相談可能!
-
Point
住宅ローンやや間取り、土地探しまで相談できる
-
Point
数ある住宅メーカーから自分に合ったメーカーが見つかる!
-
Point